~ツール無くしてポーションコントロールなし~
今回は、ポーションコントロール法とは何かを原点にもどって解説したいと思います。
今回の概略
本ブログでは、日本版ポーションコントロール法である111弁当箱法について説明をしてきました。そして、世界中で使われている他のポーションコントロールツールについても、ちょうど1年前(2024年8月)の記事で紹介させて頂きました。しかし、ポーションコントロール法とは何かについて、まだ解説をしていませんでした。実は、ポーションコントロール法の定義を明確に示した文献は見当たりません。もし、「ポーションコントロール」が、文字通り一人前の食事量(ポーション)を適正にコントロールするという意味だけなら、日本でもよく使われている「食品交換表を用いた食事療法」もポーションコントロール法ということになりますし、一人前の食事量を減量コントロールするという意味であれば、低カロリー食や、フォーミュラ食、低炭水化物食、更に極端なことをいえば肥満手術(バリアトリックサージェリー)すらポーションコントロール法といえるはずです。しかし、ポーションコントロール法は、それら他の食事療法や栄養管理法とは明らかに区別されています。今回は、「ポーションコントロール法とは何か」を、他の食事療法との判別点を中心に解説したいと思います。また、ポーションコントロールツールについても、まとめ直したいと思います。
ポーションコントロール(PC)とは
一人前・一食分の配分あるいはその食事量をポーション(portion)といいます。食品のポーションサイズ(PS)が大きくなれば、当然エネルギー摂取量は増加します。先進諸国では、過去数十年間にわたって市場の食品パッケージの分量が増加しており、それが肥満の蔓延に寄与する強力な環境要因の一つになっていると考えられています。個人のPSが大きくなる重要な要素は、「お金に見合った価値」と「ポーション認識の歪み」であると言われており (1)、コストパフォーマンスが高く単価が安くなることで、消費者はより大きなPSの食品を選択しようとするし、例えそれが推奨されるPSを超えていたとしても、市場のPSを標準サイズとして認識します。そして、より大きなPSに継続的にさらされると、ポーションの認識に歪みが発生し、より大きなPSを1回に消費するのに適切な量として認識するようになります。PC法とは、この「ポーション認識の歪み」を補正するために、PS推定スキルの向上を対象とし、適切なPSを達成しようとする食事戦略および食事療法のことをいいます (1)。
ポーションコントロール法(PC法)の特徴
厳密にいえば、PCには3つのレベルでの対策が必要とされています (2)。それらは、食品レベルの対策(商業的なスナックや食事の分量、食品ラベル等を対象とする)、集団レベルでの対策(ポピュレーションアプローチによる健康政策)、そして個人レベルの対策(食事療法や食事教育)ですが、今回は、個人レベルでの対策に限定して説明します。PC法を他の食事療法と区別する明確な定義を記載した文献は見当たりません。しかし、PC法は他の食事療法と明らかに区別されているようです。例えば、適正な一人前の食事量を教育・実践する点では、食品交換表を用いた食事療法(食品交換法)とPC法は同じですが、食品交換法がPC法として認識されることはありません。PC法の特徴は、適切な量の認識を促すために、分量の目安を示す教育的補助ツール(PCツール)を用いることにあります。
ポーションコントロールツール(PCツール)の分類
PCツールは、大きく分類してテーブルウエアとその他に分けられ、テーブルウエアでは、食器類(PCプレートやボウル、トレイ、グラス、カトラリー、タッパーウェア)と給仕用具があり、その他では、教材(食事ガイド)、デジタルツール、クッキングウエアに分類されます (3)(図)。

1)ポーションコントロールプレート(PCプレート)・ボウル・トレイ
小さいサイズの無地の皿(通常直径25cm)やボウルは、PCに有効であることが臨床研究によって示されていますが、他のダイエット戦略と併用した場合にのみその有効性を発揮し、更に、自分で食べ物を盛り付けないことや、“おかわり”をすること等の状況はPC効果を打ち消すことにつながります。
一方、単にサイズが小さいだけではなく、適切なPSになるように大きさが調整され、食品群を分画するガイドや計量目盛り等が印刷されたプレートやボール、あるいは食品群毎に3次元的に区画されたプレートでは、それ単独でも減量に効果的であることが示されています。これらのほとんどのプレートは、皿の半分を非デンプン質の野菜に、4分の1をタンパク質に、4分の1を炭水化物に割り当てたデザインになっており、食品群で分割したそのデザインのおかげで、過剰に摂取されがちな食品成分 (炭水化物やタンパク質など) の分量を制御しながら、野菜などの望ましい食品の分量を増やすのに役立ち、最終的に教育的補助用具としての役割を担います。
このプレートモデルは実用的な栄養教育ツールであり、現在では世界中の多くの食事ガイドラインに取り入れられています。オリジナルである2次元 (2D) プレートモデルは、適切な分量を教育するためのシンプルな教材として採用され、3次元 (3D) プレートを使用することで、ユーザーはこの食事理論を実際に体現できます。概念的な教材としての2Dモデルも、食事中に使用される3Dプレートも、PCツールとしての有効性が示されています (4)。
2)グラス(形状とサイズ)
人々はグラスの相対的な満杯度で液体量を判断するため、グラスの形状とサイズの両方が、飲量の認識に影響を与える可能性があります。しかし、飲料の種類(ソフトドリンクかアルコールか)や飲む状況(例えばワインは、レストランではグラスよりもボトルで飲量が決まることが多いなど)等の影響要因が多いため、グラスの形状とサイズによる飲料の消費コントロールについては、可能性はあるものの、一般化できる効果は示されていません。
3)カトラリー(フォークやスプーン)
小さなカトラリーは一口サイズと摂食速度を減らすのに役立ち、量を気にせず自由に食べられる状況では、消費される食物の量を減らすことができると報告されています。しかし、多くの状況では摂取量を決めるのは提供された食物の総量であるため、食器のサイズが摂取量に直接影響を与え、小さなカトラリーの効果は表面に現れにくいと考えられています。
4)給仕用具
容量調整された「取り分け用スプーン」などの分量コントロールを目的としたサービング器具についても、PC効果が得られる可能性がありますが、現時点では十分なエビデンスはありません。
5)教材(教育ガイド)
PC法での教育ガイドは、2Dプレートモデルによって行われ、教育的補助器具は、画像ベースのツールであり、あらかじめ分量が示された食事図、推奨食材の種類や分量のガイド、食品レプリカの分量ガイドが含まれます。プレート法は多くの国の食事ガイドラインに採用されていますが、各国の食事事情等に合わせて修正や調整が行われています。
6)デジタルツール(ウェブベースまたはモバイルアプリケーション)
テクノロジーを利用したデジタルツールの利用は、食事推奨量についての教育や栄養プログラムの順守のために期待されています。残念ながら、これらを用いた介入は、PSの意識に有意な影響を与えないと報告されており (3)、2025年8月現在でも、有望な可能性を示した報告は散見されるものの、臨床的に意義のある有効性が示されたものはありません。しかし、自動食品解析ツールや食事内容の評価ツール等、AIを用いた新たなモバイルアプリケーションの開発と利用は増えており、今後更に有効性の高いデジタルツールが開発されることが期待されます。
7)クッキングウエア(計量ポットや計量スプーン)
計量ポットはシリアル、米、パスタなどの穀物の量を管理し、計量スプーンは油やバターなどの高カロリー脂肪を計量するのに役立つと考えられますが、PCに関する有効性についてのエビデンスは示されていません。
最後に
PC法、特にプレート法は、多くの国の食事ガイドラインに取り入れられ、不健康な食事の是正や、肥満者の減量、2型糖尿病をはじめとした生活習慣病患者での病態の改善に有効性を発揮することが示されています。次回は、代表的なPC法であるプレート法について説明します。
図の説明
引用文献 (3)の分類を基に、日本でも利用可能なもので作成しています。
購入できるテーブルウエア、インターネットから入手できる教材・ガイドライン、アプリ等の例:
- プレート:Portion Perfection Plates (https://www.greatideas.net.au/portion-perfection-plate-melamine.html)
- プレートとボール:Portion Control Bariatric Plates and Bowls
- トレイ:Health Beet Kids Healthy Portion plate(https://healthbeet.org/portionplate/)
- 容量設定したタッパーウェア:Elceeo Essential Solutions ポーションコントロールコンテナキット(L.C.O. Solutions Inc.)
- 取り分け用スプーン、おたま:Cook’s Rite-Size Rite-Size Perforated Round Circle Server Set of Portion Control Utensils
- MyPlate.gov: https://www.myplate.gov/
- Healthy Eating Plate:https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/healthy-eating-plate/
- シンクヘルスアプリ: https://health2sync.com/ja/services/sync-health-app/
引用文献
1. Steenhuis IH, Vermeer WM. Portion size: review and framework for interventions. Int J Behav Nutr Phys Act. 2009;6:58.
2. Almiron-Roig E, Forde CG, Hollands GJ, Vargas M, Brunstrom JM. A review of evidence supporting current strategies, challenges, and opportunities to reduce portion sizes. Nutr Rev. 2020;78(2):91-114.
3. Vargas-Alvarez MA, Navas-Carretero S, Palla L, Martinez JA, Almiron-Roig E. Impact of Portion Control Tools on Portion Size Awareness, Choice and Intake: Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(6).
4. Jia SS, Liu Q, Allman-Farinelli M, Partridge SR, Pratten A, Yates L, et al.The Use of Portion Control Plates to Promote Healthy Eating and Diet-Related Outcomes: A Scoping Review. Nutrients. 2022;14(4):892.
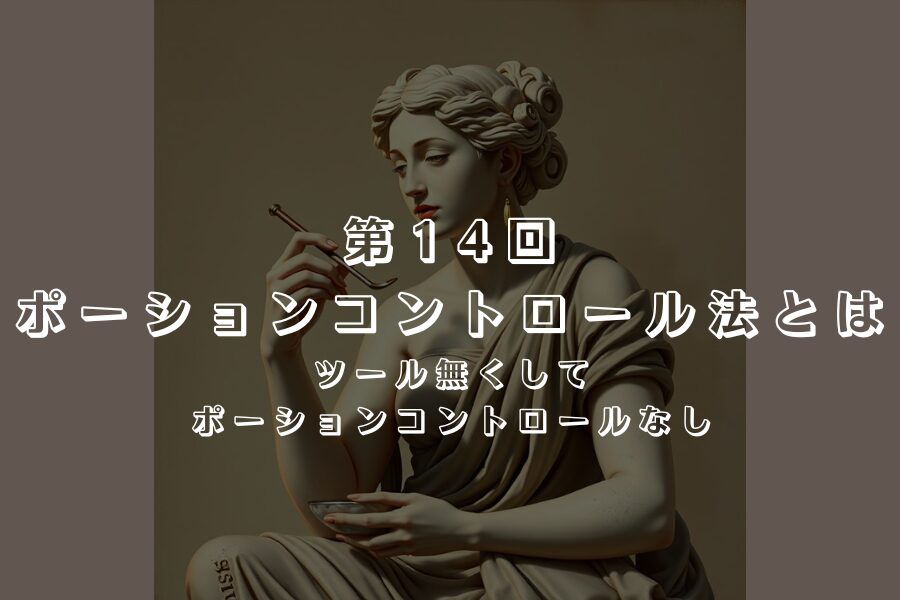

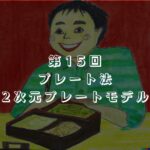
コメント